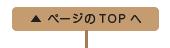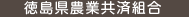カテゴリー別アーカイブ: お知らせ一覧
情報開示事項を更新しました
農業共済新聞(5月)を掲載しました
備えて安心 園芸施設共済
収入保険と同時で一層充実
徳島県吉野川市 岡田要介さん
_22歳からハウスナスを栽培しています。園芸施設共済には、ハウスナス栽培を始めた当初から、附帯(ふたい)施設と内作物の補償を付けて加入しています。加入当時、台風がよく来ており、ハウスに何かあったら経営が立ち行かなくなってしまうということで共済に入ろうと思いました。加入して間もない頃にナスの青枯病が出て、共済金に助けられました。
_2021年5月には、ハウスに火災が発生しました。施設本体から内作物のナスまで被害を受けました。そもそもは台風などの自然災害や内作物の病害などを心配していたのですが、まさか火災が起こるとは思ってもみなかったので、加入していて本当に良かったです。
_昨年から収入保険にも加入し、内作物も補償対象となりました。近年、野菜相場が全体的に下がっており、ナスは個人出荷なので価格の下落があった場合の対策になります。さらに、内作物だけの補償だったのが、露地で栽培しているブロッコリーも対象に加わるのは心強いです。
_洪水で吉野川の本流も昔から変わっています。台風も勢力が年々巨大化していて、この場所にもどんな水害が起こるか分かりません。大きな台風などが来てしまうと、普通の家でも飛んでしまうから、ハウスなんかすぐ飛びますね。自分の住む所だけ大丈夫だなんてことはないと思います。いろんな事態に準備をしておかなければいけません。
_現在、ナスの品種は「ラクロ」ですが、新品種の「PC鶴丸」を検討しているところです。また作業のメインになりつつある息子に後継者として経営を譲る準備に入っています。園芸施設共済と収入保険を合わせることで、さらなる備えと安心が得られると思っています。

広報紙第33号を掲載しました
令和6年度より現金での共済掛金等の納入は 原則廃止とする取組みを実施します
農業共済新聞(3月)を掲載しました
水稲育苗用培土80万箱分製造
地域農業の維持に貢献
徳島県阿南市 ㈲谷産業
_水稲育苗用の培土を約4千㌧製造する有限会社谷産業(阿南市長生町、代表・谷和紀さん=63歳)。出荷する育苗用培土は、JA東とくしま、JAアグリあなん、JAかいふ、JA板野郡のほか、個人で育苗をする農家へも卸す。水稲用だけではなく、野菜や花の育苗用培土も出荷している。
◆
_育苗用培土を作るようになったのは、田植機の普及が始まった1970年ごろ。谷さんの父が育苗用培土を製造し、地元の育苗センターへ出荷したのが始まりだという。以降、製造業者が減少。現在は県南部では谷さんだけとなり、水稲育苗箱約80万箱分の培土を作るまでになった。
県内の育苗用培土は、山間地で取れる赤土を太陽光で自然乾燥させて製造するのが一般的。谷さんは赤土をローラーでつぶし、重油バーナーで加熱乾燥させるという工程を追加した。加熱乾燥させることで殺菌作用があるほか、倉庫内で作業するので天候に左右されず安定して供給できる利点がある。
_雑菌の繁殖を抑制するため、山から運んできた赤土は1年ごとに使いきり、翌年には新しい土から育苗用培土を製造。谷さんは「加熱殺菌工程を入れることで消毒回数を減らす効果が期待できる。土を手で直接触る農家の方に、より良い状態で触ってほしいという思いがあって、ずっとこの方法を採っている」と話す。
_育苗用培土の製造・出荷が終われば、谷さんは「農事組合法人ファームおおたに」の一員として水稲栽培を始める。同法人は、地域農業をしやすい環境づくりを理念に、2017年に設立。大型機械の共有や圃場整備、補助金申請などの事務整理、ドローン(小型無人機)を使用した農薬散布の効率化、農作業のノウハウの共有など、個人で農業を続ける際に課題となる点にフォーカスした活動に取り組む。
_地元用と県内各地の育苗用培土作り、法人の運営など、仕事は大がかりなものになったが、谷さんの根底にあるのは「地域のために役立ちたい」という思い。「いつまでも地元の、ひいては県内の農業が続いていくことを願っている」と話してくれた。
 |
 |
| 培土の品質を確認する谷さん | 育苗用培土を製造する機械 |
農業共済新聞(2月)を掲載しました
野菜収穫、サイクリング
好評の体験プログラム
東みよし町 農家民宿「岩野家」
先代から農業を引き継ぎ、主食用米150㌃、野菜70㌃を栽培する東みよし町の岩野幸男さん(68)と万里子さん(68)夫妻。家業を生かし、収入につながることを始めようと夫婦で相談し、農家民宿「岩野家」を2019年12月に開業した。徳島県の農村文化や自然などに触れられる体験プログラムを企画している。
作物を育てる大変さや充実感を味わってほしいと考え、提供する巻きずしや煮しめなどの料理には宿泊者が自ら収穫した野菜を使う。自然の雄大さと四季折々の景観を楽しんでもらえるように、体験プログラムには特別天然記念物の加茂の大クスのほか、吉野川沿いなどを巡るサイクリングを組み込む。
宿泊客からは「普段の生活では味わえない体験ができる」と好評だ。修学旅行で訪れた高校生との交流が続き、「全国にたくさんの孫ができたよう」と楽しそうな万里子さん。「田舎のおばあちゃんの家に来たような感覚で楽しんでもらいたい」と笑顔で話す。

笑顔で出迎える岩野さん夫妻
農業共済新聞(1月)を掲載しました
〈特集〉私の登竜門
障がい者の就労支える
徳島県阿波市 宮田 大貴〈みやた・たいき〉さん(26)
「障がいのある弟と一緒に働く場所をつくりたい」という思いがきっかけで、父の地元の阿波市で2020年に農業を始めました。
考えに賛同してくれた大学時代の仲間3人と、農業知識ゼロの状態からスタートしたので、土地の整備やハウスの建設など挑戦続きの4年間でした。
イチゴ栽培の師匠や地域の方の支えがあったおかげで、ハウスイチゴをはじめ原木シイタケも拡大しました。
イチゴをメイン作物に選んだ理由は、作業の種類が多いからです。同じような障がいでも、十人十色の特性があります。作業の種類が多いからこそ、それぞれの特性に合った作業を見つけられるのではないかと考えました。
目標は、NPO法人の設立と、研修生の受け入れや研修が修了した後に従業員として雇用することです。老若男女、障がいの有無を問わず、集い楽しめる場所をつくり、働きに来るのが楽しみになるような環境を整えたいです。

「収穫期以外はキッチンカーで販売しています。イチゴのスイーツのほかにラーメンもあるので、甘みが苦手な方にも楽しんでもらいたいです」と宮田さん
「大雪に伴う農作物等管理対策について」
徳島県立農林水産総合技術センター高度技術支援課より発表されておりますので、
ご注意ください。
大雪に伴う農作物等管理対策について(徳島県へリンクします)
つきましては、今後の情報に十分ご留意の上、適切な損害防止に努めるとともに、
被害が発生した際は、遺漏なき被害の申告をお願いいたします